
日本人の実に8割以上が「対中感情は良くない」と回答しているそうだが、私も嫌い。彼らは所構わず大きな声で喋りちらすし、マナーもよくない。銀座になんて来ないでほしい。
ただ、経済という観点からは無視できない存在であるのも確かだ。なんたって、日本の市場は上海市場次第。(というか、日本は海外の影響を受けすぎる)
ただ、嫌いといいつつも、今年に入ってからは「中国関連本」を割と好んで読んでもいる。嫌いという感情は「興味がない」とは全く異なるもので、意識するからこそ嫌いなのかもしれない。
本書もまた中国に関連する本である。
タイトルの「和僑(わきょう)」というのは、本書によれば、もともとは中国人妻をめとったファンキー末吉という人が、華僑をもじって発明した言葉らしい。
その言葉を素直に解釈すれば、「海を渡った日本人」なのだろうが、主に「中国でビジネスを立ち上げた日本人」という意味で使われているのだという。
しかし、「僑」という字は、わたりもの、故郷を離れ他国に住む人のほかに、仮住まい、旅、出稼ぎという意味もあるため、本書では、「中国大陸で、僑い(かりずまい)をしたり、僑(たび)をしたり、僑(でかせぎ)をしたりする和人の総称として使われている。
サブタイトルにある「農民、やくざ、風俗嬢」たちも、その「和僑」なのだ。
より具体的にいえば、雲南省の片田舎の少数民族の村に暮らしている2ちゃんねらー、上海で組みを立ち上げたやくざ、マカオに出稼ぎにいく風俗嬢などである。
ああ、こういう人も世の中にはいるんだなぁという視点で読むに、とても面白い。

総論として、著者は「彼らは中国に、昔の古き良き日本を見て、そこに惹かれている」とまとめているのだが、それには私はちょっと違和感を感じた。
その是非は読む人自身にゆだねるとして、それよりも、枝葉のエピソードは魅力的だ。
「こんなところに日本人」というテレビ番組があるのをご存知だろうか。世界のド田舎の村に住んでいる日本人を、タレントが訪ねていくというものなのだが、それに近い感じがある。
2ちゃんねるのスレッドや噂をたよりに、著者は「和僑」たちを訪ね歩くのだ。
例えば、マカオで働く日本人風俗嬢を探したときは、著者はマカオ式サウナ(希望すれば性サービスも受けられる)に行くのだが、そこで学生時代の彼女にとてもよく似た女の子を見つけて動揺したりする。こうした個人的なエピソードが結構面白い。
「和僑を通して日本を見る」という仕立てになってはいるが、感じたのは「彼らが中国に惹かれるのはなぜなのか」という問いだったように思う。
それは、とりもなおさず、中国通で高校生の頃から中国語を勉強していたという著者自身の問いでもあるのだろう。
中国は、一党独裁で、日本に比べると何かと制限が多い国だ。数年前に起きた温州市の鉄道脱線事故では、隠蔽のために列車を埋めて世界を驚かせた。その上、尖閣諸島等領土をめぐる問題では、ならず者といっていいほどの横暴さを示す。日本人の対中感情が悪化するのも当然というものだ。
なぜ、そんな国に惹かれるのか?
これに、著者は”エスニシティと、中華人民共和国という国家は似て非なるものだからだ”という答えを出している。
なるほどなぁと思う反面、私はその全てに納得できるわけでもない。
この国家というものについては、本書の続編ともいえる「境界の民」で、掘り下げられているようである。

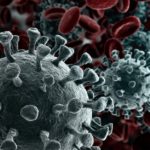




コメントを残す